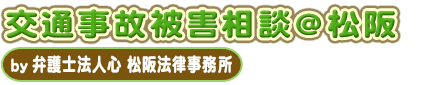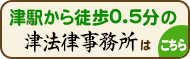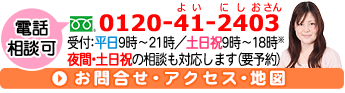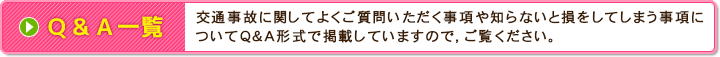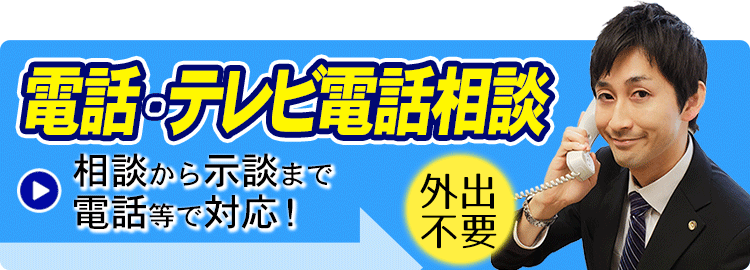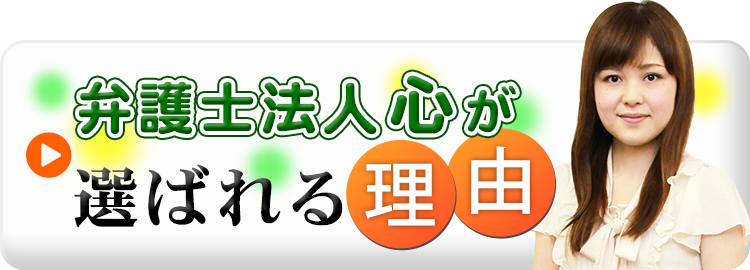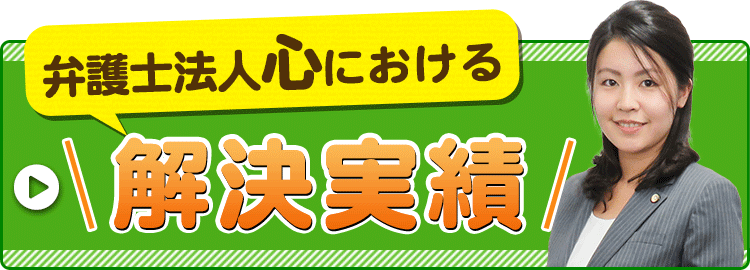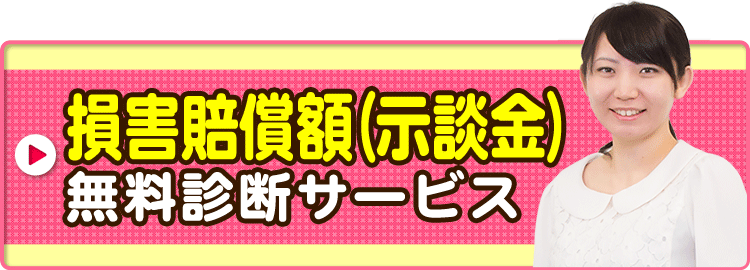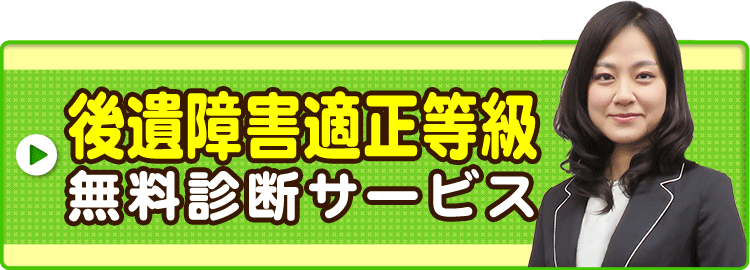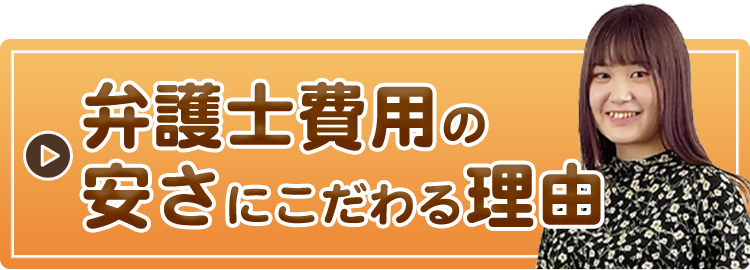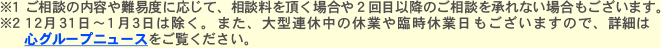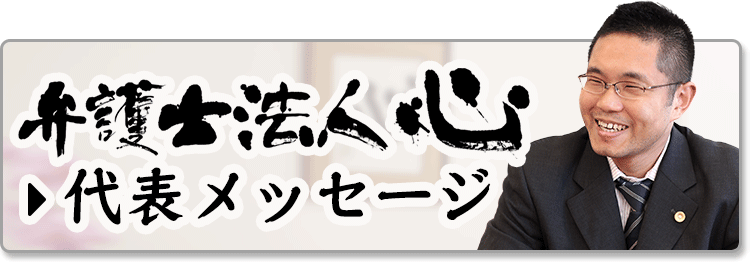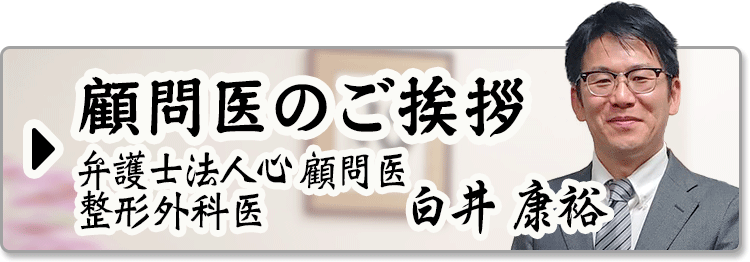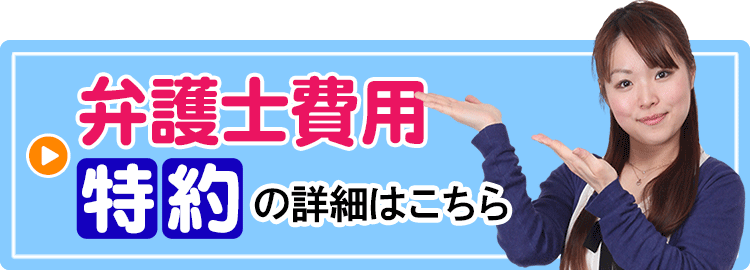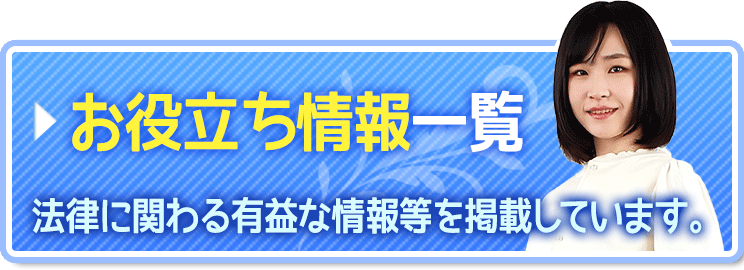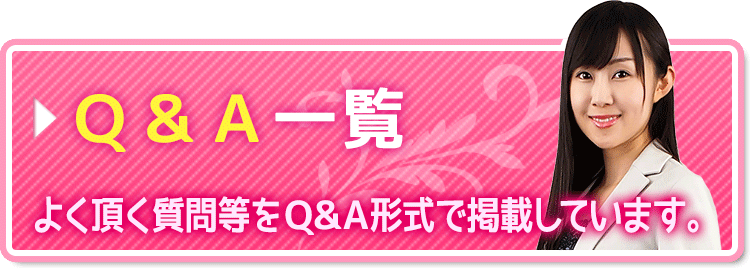高次脳機能障害になった場合の症状固定の時期
1 症状固定とは
症状固定とは、「治療を行っても、その効果が期待できない状態・症状の改善が見込めない状態」になったことをいいます。
この症状固定の時期は、交通事故によりどのような傷害を負ったのかという受傷内容により大きく異なります。
2 高次脳機能障害における症状固定の時期
⑴ 高次脳機能障害における症状固定時期の特徴
症状固定とは、上記のとおり治療の効果に関わる事項になりますので、医師の判断によります。
通常、いわゆるむち打ち案件の場合には、事故から6か月を経過すると症状固定とされることが多いようですが、高次脳機能障害の場合、事故から6か月を経過した時点で症状固定と判断することは早いと思われます。
高次脳機能障害の場合、脳の損傷が進んでいる状態ですが、リハビリ等で回復することもあれば、あとから様々な症状が出てくることもあります。
そこで、高次脳機能障害の場合、症状をきちんと把握するため、リハビリの経過はもちろんのことですが、日常生活や職場での状況等をしっかりと確認してから、症状固定か否かを判断することが必要です。
そのため、事故から1年以上経過してから症状固定とすることが多いようです。
受傷者の年齢によっても以下のように個別に検討が必要です。
⑵ 受傷者が子どもの場合
後遺障害等級が1級や2級に該当するような重症案件の場合、1年程度で症状固定としても、大きな問題とはなりません。
しかし、それ以下の等級に該当するような案件の場合には注意が必要です。
子どもの場合、学校生活への適応にどの程度の支障が生じているのかを確認・判断する必要があります。
そのため、ある程度の経過観察が必要となりますので、受傷者が子どもの場合、成人の場合と比べ、症状固定時期が遅くなるケースが多く見受けられます。
子どもが未就学児の場合には、就学を待って症状固定時期を判断することもあり、そうすると、相当長期間になることがあります。
⑶ 高齢者の場合
高齢者の場合、成人と同様、事故から1年程度で症状固定とされるケースが多いです。
ただし、高齢者の場合、年齢による認知機能の障害も存在していることがあります。
そのため、症状固定となった後、期間が経過し、症状が悪化した場合には、通常の加齢による変化を超えた悪化が生じていると評価できる場合には、上位等級への認定変更の対象とすると扱われています。
高次脳機能障害で弁護士をお探しの方へ むちうちで弁護士をお探しの方へ